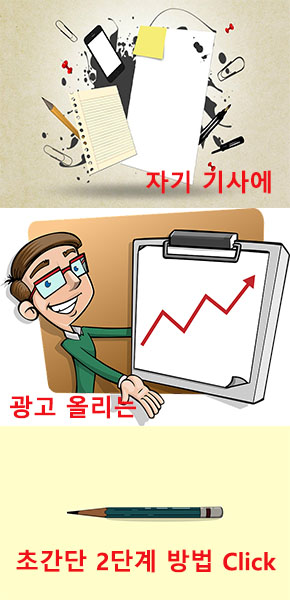日本の米価、16週連続で上昇中
日本国内の米価上昇が止まらない。4月14日から20日までの1週間、スーパーにおける5キロあたりの平均販売価格は4220円となり、前週からさらに3円上昇した。これで米価は16週連続の上昇となった。昨年同時期の2088円に比べ、2倍以上に跳ね上がっている。販売量も前年同期比で14.9%増加した。
政府は今年に入ってすでに3度目の備蓄米を市場に放出しているが、価格上昇に歯止めはかかっていない。備蓄米が一般のスーパーに出回っていないとの指摘があり、3月の2回目の備蓄米入札以降、米卸業者ですら十分に確保できていないという報道も相次いでいる。
総務省統計局によると、2024年の米価はすでに前年比46.6%上昇しており、1971年のオイルショック以来、最大の上昇幅となった。同年の消費者物価指数(CPI)は前年比2.7%の上昇にとどまっており、米価高騰が物価全体の押し上げ要因となっている。
昨年の異常気象や豪雨が、米価上昇の主な原因とされる。主要産地である新潟県や秋田県では、台風や病害の影響で予想収穫量の8割程度しか確保できなかった。
さらに、2024年秋に西日本を襲った大地震により物流網にも打撃が加わり、消費者の不安心理が広がったことで、米の買い占めが発生。市場の需給バランスが崩れた。
政府も有効な対応策を打ち出せずにいる。備蓄米放出も「焼け石に水」となっており、価格引き下げにはつながっていないのが実情だ。東京大学大学院 農学生命科学研究科の安藤光義教授は、現地メディアの取材に対し「備蓄米は低価格で供給されているが、卸業者が昨年秋以降、高値で米を仕入れているため、簡単に価格を下げることができない」と指摘している。
米価の上昇に伴い、食品全体の価格も上昇傾向を強めており、国民の実質的な購買力が低下している。昨年の日本の家計全体の実質消費支出は1.1%減少。エンゲル係数は28.3%に達し、1982年以来、43年ぶりの高水準となった。
米や基本食材の値上がりによる生活苦から、消費者ローンなどの利用も急増している。昨年末時点での消費者ローン残高は4兆4117億円に達し、前年比5.4%増加した。
米価高騰への対策が難航する中、政府は国民への直接的な生活支援策として、1人当たり50万円の緊急現金給付を検討している。
ただし、このような一時的な現金給付は根本的な解決にはならず、むしろ不必要なインフレを招く恐れもあり、日本政府としても慎重な対応が求められている。
[저작권자(c) 한중일 경제신문, 무단전재및 재배포 금지]