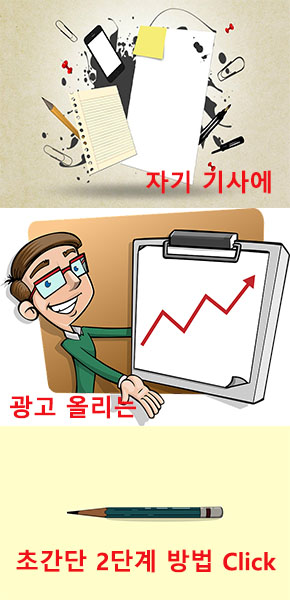【社説】「黄色い封筒法」――労働権強化の名分の裏に隠れた投資リスク
国会はついに「黄色い封筒法」を可決した。三度目の挑戦の末に実現した結果である。労働界は「20年来の悲願」として喝采を上げたが、企業や投資家の不安はそれだけ深まった。新法は元請け企業にも交渉義務を課し、ストライキに伴う損害賠償は違法・暴力行為に限定する。趣旨は理解できる。しかし、その手法とスピードは韓国経済の予測可能性を大きく損なうおそれがある。
とりわけ「使用者」概念を拡大し、元請けを交渉相手とする条項は曖昧だ。どこまでが通常の発注・品質管理であり、どこからが労務支配となるのか、その線引きは不明確である。結局、現場では紛争と訴訟が増え、そのコストは企業競争力と投資環境の悪化に直結せざるを得ない。
外国人投資家の反応はさらに敏感である。在韓米国商工会議所が即座に懸念を表明したのは、単なる儀礼的な発言ではない。世界の企業は投資先を選ぶ際、「法的安定性」を最優先する。今回の法律によって韓国が「予測不可能な国」と認識されれば、新規の外国直接投資は萎縮し、国内企業の海外増設は一層加速する可能性が高い。とりわけ造船・自動車・電池産業では、グローバルなサプライチェーン競争の中で納期と生産の安定性が何よりも重要であり、交渉構造が複雑化すれば韓国の地位は一段と揺らぐであろう。
国際比較でも、韓国は相対的に強硬な道を選んだ。英国は違法ストに損害賠償の上限を設け、ドイツは「平和義務」違反に限って責任を問う。日本は正当な争議行為には損害賠償を禁じているが、元請け交渉義務を一律に拡大したことはない。米国は元請け責任の範囲を狭く解釈する一方、違法なボイコットには巨額の賠償を課す。これに対し、韓国は賠償制限と元請け交渉義務拡大を同時に進め、均衡装置なしに労働側へ傾斜した格好である。
無論、労働界の主張に耳を傾ける必要もある。過度の損害賠償や仮差押えが労働者を法廷に追い込み、対話自体を妨げてきた現実は確かに存在する。合法的なストが保護され、交渉文化が根付けば、長期的には労使関係が健全化する可能性もある。しかし問題はその過程である。短期的な衝撃を吸収するセーフティネットや精緻な指針が整備されなければ、この法律は新たな対立の火種となりかねない。
政府と国会はいま、政治的な勝利感に酔っている場合ではない。施行まで残された6か月間で、「使用者性」の境界や交渉手続きを明確にし、不必要な混乱を最小化する運用指針を示さねばならない。そうでなければ、韓国は労働権強化という成果とともに、投資流出という代償を同時に背負うことになるだろう。
[저작권자(c) 한중일 경제신문, 무단전재및 재배포 금지]