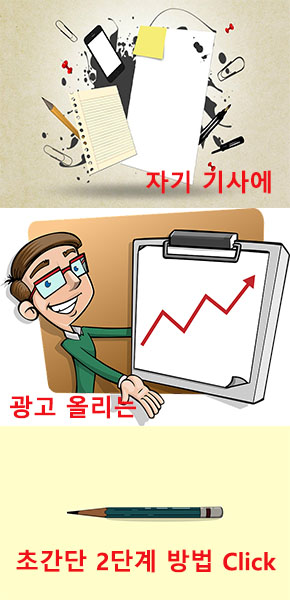【解説】米中関税戦争、ASEAN諸国の選択は? ベトナムの事例
トランプ米大統領の相互関税政策は事実上、米中間の関税戦争に圧縮されている。 米国が中国を除くすべての国に対して相互関税率の適用を90日猶予した反面、中国に対しては累積関税率を145%まで引き上げ、中国側も125%の関税率でこれに対抗している。 中国がレアアース輸出などのもう一つのカードを取り出したことで、両国間の衝突は強対強に突き進んでいる。
一方、両国は他の国々に対して、いわゆる「味方作り」戦略を駆使している。 米国は、他の国々に対して、米国と中国のどちらか一つの国を選択せよという強硬なメッセージを出すと同時に、相互関税率の適用を90日猶予し、期間中、交渉の道を開いている。 中国は特にアセアン地域を中心に自国の新しい市場の可能性を説き、他の国々を引き入れることに注力している。
ベトナム統計庁によると、2024年のベトナムの名目GDPはアセアン国家中4位の4763億ドルを記録した。 同期間、ベトナムの対米輸出額は1195億ドルだった。 経済成長率は前年比7.09%、対米輸出額は23.17%大きく増加した数値だ。
数値上から見れば、ベトナムの対米輸出額は自国GDPの25%を超える数値だ。 ベトナム経済がどれほど対米輸出に依存的なのか、難なく把握することができる。 さらにベトナムにとって米国は最大の輸出国として自国輸出の29.4%を占めている。 ベトナム経済が対米輸出にかかっていると言っても過言ではない。
中国も重要な交易国だ。 昨年、ベトナムの中国向け輸出額は612億1千万ドルで、米国に次いで2位を記録した。 むろん、米国に比べて半分を少し上回る金額だが、やはり相当な規模だ。
同期間の輸入額は約1140億2千万ドルで、ベトナム全体の輸入額の29.95%に達している。 断然第1位の輸入対象国だ。 中国としてもベトナムとしての重要な交易対象国に違いない。
ここ数日間、習近平主席はASEAN諸国を歴訪している。 もちろん、今回の関税戦争で彼らとの結束が重要なカギになるという判断によることだ。 14日から2日間ベトナムを訪問中、習近平主席は今回のトランプ大統領の相互関税賦課方針について一方的ないじめだと指摘し、今後のベトナム商品に対する中国の開放政策などに言及したという。
中国とベトナムのマスコミは両国首脳が45条項の協約に署名したと報道したが、その詳細は明らかにされなかった。 相互関税と関連した内容が中心だろうという推測だけが出ている。
政治的にベトナムと中国の両国は、近い関係とは言えない。 しかし、今回の訪問と関連してベトナム側は習近平主席を非常に歓待する雰囲気で迎えたと両国メディアは報道している。
これに対してトランプ大統領側の反発も激しい。 今回の習近平主席の巡回と関連し、トランプ大統領は「米国に対抗するための計略を練るためのことだ」と非難し、自身の気持ちを表わした。 中国であれ米国であれ、どちらか一方を選べ」という極端な発言まで流れている。
数値が示すように、ベトナムとしては対米輸出が円滑でない場合、自国の経済自体が動揺せざるを得ない状況だ。 その上、中国との交易関係においても構造的弱点がある。
中国がベトナムの最大輸入対象国になった裏面には、ベトナムが中国商品に対する迂回輸出基地としての役割をした側面がある。 中国商品の対米輸出が難しくなり、ベトナム企業が地域的利点を利用し、中国商品を輸入して米国に輸出することが慣行のように続いてきた。 米国としても、この問題を常に疑って監視する立場を取ってきた。
これを意識したためか、ベトナム政府が今月に入って中国産商品の対米迂回輸出に対する調査と取り締まりに乗り出したという一部報道が出たりもした。 特に、中国産製品がベトナム産で原産地規定を破る事例に対して集中的な調査が行われていると伝えられた。 習近平主席との雰囲気の良い会談とは別に、必要な措置は取っているという意味だ。
ただ、このような措置がどれほど持続できるかは未知数だ。 迂回輸出が完全に滞る場合、自国経済に及ぼす打撃が小さくないということをベトナム政府もよく知っている。
実際、ベトナム側が眺める中国側市場に対する展望は必ずしも明るいとは言えない。 直ちに中国市場の購買力に対する懐疑が生じるのは仕方がない。 今のところ、中国自体も輸出の道が閉ざされた過剰生産された商品を内需で解決しなければならない状況だ。 海外商品を消化する余力がどれだけ残っているか未知数だ。
その上、ベトナムの対米輸出品が大部分繊維、電子など軽工業中心になっているだけに、中国との市場関係が補完関係というよりは競争関係と言える。 軽工業商品の生産余力が依然として生産過剰である中国市場に浸透する余力が残っているかも未知数だ。
2024年のベトナムの対米輸出黒字額は千億ドル以上と把握されている。 事実上、対米輸出額のほとんどが黒字であるわけだ。 この期間の対米輸入額は130億6000万ドルに過ぎなかった。
問題は、現在としてはベトナムが対米貿易黒字を減らす適当な方法がないという点だ。 ベトナムの購買力そのものが著しく足りないからだ。
その上、米国側の相互関税率計算公式はただ相手国に対する赤字規模と米国側の輸入規模だけを変数にするため、貿易黒字を減らさずに米国側をなだめる方法が適当でないのが現実だ。
対米貿易黒字の規模を減らすためのベトナム政府レベルの努力はもちろん続いている。 ボーイング航空機とLNG(液化天然ガス)の追加購買の約束、スターリンク衛星サービスのテスト運営の許容などの努力が続いている。 しかし、政府レベルの努力だけで巨大規模の貿易黒字を減らすには限界がある。 いつまでも持続できるレベルの努力でもない。
4月10日、ベトナムは自国の代表団を素早く米国に送り交渉を試みた経緯がある。 さらに、ベトナム政府は米国製品に対する輸入関税率を0%に引き下げるという意思を明らかにした。 だが、米国側の反応は依然として冷ややかな状態だ。
今回の米中間関税戦争がベトナムとしては必ずしも不利な点だけがあるわけではない。 ベトナムこそ、中国産製品の対米輸出の道が閉ざされれば、反射利益を得るのに最も良い位置にある国の一つだ。 軽工業製品中心のベトナム輸出品のうち相当数は依然として中国と競争関係に置かれているためだ。
90日間の猶予期間中、米国側は中国以外の国々に対して10%の関税率を適用したが、ベトナム企業としてはこの程度の関税率ならまだ耐えられると判断している様子だ。 むしろ猶予期間中に最大限の押し出し輸出で、期間中に史上最大の対米輸出規模を達成できるという見通しも出ている..
その上、関税戦争が長期化する場合、中国を離脱した海外企業がベトナムを新しい投資先として探すことになる可能性も依然として残っている。 このような現象はトランプ政権1期目の中国に対する貿易規制当時、すでに一度発生した前歴がある。
ベトナムとしては、中国との円満な関係を維持しながらも、米国の機嫌を損なってはならない厳しい状況に置かれている。 二者択一という極端な状況まではいかなくても、不便な状況であることは間違いない。
対外関係というのがいつもそうであるように、ベトナムとしては米側の要求を最大限受け入れながら、中国との友好的関係を維持するための努力を続けていくものと見られる。 要するに、米側が要求するようにどちらか一方に偏ることはないと判断される。 同時に、今回の両国間の関税戦争で、自分たちの隙間利益を最大限確保できる案づくりに奔走するものとみられる。 もちろん産業構造の高度化などのような長期的戦略を並行していくことは言うまでもない。
ベトナムだけでなく、他のASEAN諸国も状況は似ているものと見られる。 好むと好まざるとにかかわらず、現在アセアン諸国が強要されている共通の境遇と言える。
[저작권자(c) 한중일 경제신문, 무단전재및 재배포 금지]